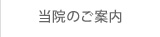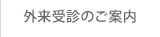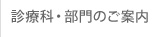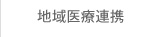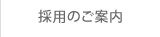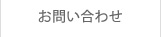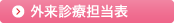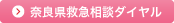- ホーム
- 診療科・部門のご案内
- 大和高田市で整形外科をお探しの方へ
整形外科外来診療担当表
整形外科の紹介と特色
整形外科は運動器(関節・骨・靱帯・筋肉・末梢神経・脊髄)の治療を担当する科です。
地域医療を担う当院の一翼として、整形外科一般の診療を行っていますが、なかでも、①股関節・膝関節・肩関節の手術、②高齢者の骨折・関節疾患の手術、③エコーを用いた治療に、特色を持った診療を行っています。
外傷(骨折)の治療・・・エコー・ブロック・関節鏡も積極的に導入しています
近年高齢化が進み、転倒などの外傷により骨折してしまう方が増えてきています。特に、股関節周囲の骨折や背骨の骨折などをきたした場合、いわゆる寝たきりの原因となってしまうこともしばしばあります。また、転倒する時に手をついてしまうと、手関節や肩関節の骨折をきたしてしまうことがあります。いずれの骨折も大きなケガであり、運動機能にダメージを与えることは言うまでもありません。我々、整形外科は、そういった骨折の治療として、必要であれば積極的に手術加療をきちんと行い、術後のリハビリテーションを充実させることで運動機能を少しでも維持できるように努めています。退院後の介護の調整なども含め、患者様ひとりひとりの生活の質を保てるように、日々診療を行っております。また、骨折や脱臼などの整復の際に、超音波装置(エコー)を用いて神経ブロック麻酔を行うことにより外傷に伴う痛みを緩和することなどの工夫も行っております。また、手術では、関節鏡を使用した低侵襲な手術も積極的に行っています。
股関節の治療
脚の付け根の痛みおよび歩行障害の原因として、股関節が原因の場合があります。
股関節に発生する病気として、変形性股関節症、大腿骨頭壊死、関節唇損傷などがあります。その中でも、変形性股関節症は、年齢と共に筋肉が衰え体重が増加しやすい平均40~50歳の年齢に発症しやすい病気です。痛み止めを飲んでも歩行時の疼痛が軽減しない、特に夜間に疼痛で目が覚める、痛みでなかなか寝付けない状態が長期間続き、改善の見込みがなければ、手術を考慮してよい時期かと思います。股関節の手術には、自分の骨で治す方法と人工の関節をいれる方法の2種類あります。
人工の関節をいれる方法は、人工股関節全置換術といいます。人工関節は、股関節の疼痛はよくなり歩行障害も改善します。しかしながら、手術後の合併症として、感染、脱臼、人工関節のゆるみ、肺梗塞などがあります。合併症の予防には、術前計画(セメント使用の有無、進入法、手術機種の選択、臼蓋ソケットの設置位置、臼蓋ソケットの被覆率、脱臼防止のための軟部組織の修復)および手術時間の短縮、出血量の減少が重要です。
当院整形外科では、合併症の予防には十分に注意をはらい、より安全な手術を心がけています。また、充実したリハビリのスタッフとともに手術後の十分な機能回復をめざしたリハビリをさせていただきます。股関節の痛みでお困りの方は、是非ご相談ください。
膝関節の治療
軟骨・靱帯損傷など、幅広く対応しています。
1)軟骨の疾患・外傷
膝には骨をおおう関節軟骨と、膝に特有の半月板という軟骨があります
①半月板の疾患・外傷
半月板は、膝が受ける衝撃を緩和し、安定化させる働きをしますが、大部分は血行がなく、自然治癒が進みません。成人後は、加齢による質の低下も加わります。そのため、若年層では、スポーツや外傷など原因がはっきりしたケースや、円板状半月板と呼ばれる損傷が生じやすい先天的な形状での発生が多く、一方、中高年以降では、これといった原因を想起できないケースも増えてきます。症状は、起立動作や曲げ伸ばし、正座や運動等での痛みが多く、損傷部が関節内で引っかかって、痛くて曲げ伸ばしも困難になるロッキングと呼ばれる状態になるケースもあります。
治療は、原因となっている損傷部分を切除して、症状を消退させ、損傷の拡大も防ぎます。血行がある部位など、癒合が望める部位の損傷は縫合を行い、可能な限り半月板の温存をはかっています。円板状半月板の損傷は、正常に準じた形状にする形成的切除を基本とした治療を行います。手術は、関節鏡を用いた小切開で治療を行いますが、全ての半月板損傷に手術が必要な訳ではありません。診察や検査を行って、手術の回避が可能か、慎重に判断して説明しますので、お気軽に受診してください。
※内側半月板の後根損傷の治療に注力しています※
近年のトピックとして、内側半月板の後根損傷があります。通常の半月板損傷が、半月板本体に生じる損傷であるのに対して、後根損傷は、半月板の後端部が骨に付着する部分で切れるタイプです。これが起こると、内側半月板を全部失う損傷を受けたのと同等の状態となるため、骨への負担も急に強くなり、骨壊死と呼ばれるトラブルを続発して、安静時でも膝に痛みを感じるようになることもあり、それに引き続いて短期間で急速に関節症が進行して、人工関節置換などの治療を余儀なくされるケースも、通常の半月板損傷と違って多いことが問題となっています。
50~70歳くらいに発生しやすく、典型的には、階段や段差の昇降時や、ちょっとした跳躍などで、ブチッといった異音とともに、膝の後内側(膝の裏側)に痛みが生じます。
年々、治療方法が発達し、損傷した後根部を元の付着していた位置に作成した小さな骨の穴に引き戻して逢着する手術で、急速な関節症の発生の多くを防ぐことが可能になりました。
後根損傷は、当院の膝MRI(2018年1月~2019年10月の20ヶ月間)の調査では、50歳以上の7.2%、内側半月板損傷の10%を占め、頻度も比較的多い損傷ですが、まだ充分認知が進んでいないため、診断漏れとなるケースも生じています。
当科では、後根損傷を治療する手術を積極的に行っています。症状に思い当たる方は、是非、受診してください。また、クリニックの先生方からの御紹介もお待ちしています。
②関節軟骨の疾患・外傷
骨をおおう関節軟骨は、膝が受ける衝撃を緩和しますが、血行がなく損傷を受けると半月板と同様、自然治癒が進みません。成人後は加齢による質の低下も加わり、損傷・摩耗が蓄積します。
若い年齢層ではスポーツや外傷での部分的な軟骨の剥離等の損傷が多く、小規模な損傷には剥離部の骨に小さな穴を開けて、血行を誘導して治癒機転をはかる骨穿孔を、比較的大きなものは、自家軟骨移植を行って損傷部分をおおいますが、いずれも関節鏡を利用して低侵襲に治療します。
一方、中高年以降で問題となる変形性関節症は、内側半月板の後根損傷などに続発した骨壊死など短期間で急速に進行するタイプや、長年の仕事や日常生活での負荷に、体重等の要因も加わって、加齢によって徐々に軟骨が摩耗することによって、骨の変形も伴って進行するタイプがあります。いずれも、症状が軽ければヒアルロン酸の注入や外用薬、適正な方法による筋力強化などの運動療法が治療のメインとなりますが、これらの治療では効果が得られなくなった場合は、骨切りや人工関節置換の手術を行って、症状の改善をはかります。
人工関節置換は、特に70代半ば以降の方には第一選択となる手術で、痛みの低下や歩行の改善等に安定した効果が得られます。人工関節置換の手術後は、関節の骨をおおう金属や合成樹脂の部品のゆるみや損耗を防止するため、ウォーキングやゴルフを趣味で楽しむことは問題ありませんが、ジャンプ動作や負荷が強くなる運動や仕事は控える必要があります。農林業や一定の負荷のかかるスポーツの継続を望まれる方や、(人工関節の耐用年数を考慮して)60代以下の年齢層の方で、軟骨の強い損傷が関節全域には及んでいない方には、人工関節を回避して、荷重軸を移行し残存軟骨を活用する骨切り術を行っています。骨切り術は、一般に人工関節より、手術後の可動域(曲げ伸ばしできる範囲)を多くできます。
2)靱帯の疾患・外傷
関節安定性に重要な靱帯の外傷には、内側側副靱帯(MCL)損傷や前十字靱帯(ACL)損傷、内側膝蓋大腿靱帯(MPFL)損傷などがあります。内側側副靱帯損傷の多くは外固定や装具着用で治療できます。前十字靱帯は関節内靱帯で、損傷すると外固定等をしても靱帯機能の回復は難しく、放置すると内側半月板等の軟骨損傷を続発することも多いため手術治療をします。当科では、主として自家屈筋腱を用いた二重束再建方法を行っています。
内側膝蓋大腿靱帯(MPFL)損傷は、膝蓋骨脱臼に伴って生じます。外固定・装具治療をしても脱臼が再発する場合、自家屈筋腱を用いた再建を行います。(先天的な骨形状の要因が強い場合は、骨移行による手術治療を選択することもあります)
肩関節の治療
中高年の方に好発する肩関節疾患に肩関節周囲炎(いわゆる四十肩、五十肩)があります。患者さんは肩の痛みと可動域(動かせる範囲)の制限、例えば髪の毛を洗えない、頭の上の棚の物に手が届かない、夜寝ている時に肩がうずいて眠れない、寝返りが打てない、服の着脱が困難であるといった症状を訴えられます。治療はまず痛みをやわらげるために消炎鎮痛剤などの薬物療法やリハビリテーションを行います。また局所麻酔薬やヒアルロン酸製剤や抗炎症作用を持つステロイドを関節内に注射をすることがあります。患者さんの多くはこういった保存加療で症状が緩和されますが、中には症状が改善されず長引いてしまい、精査すると肩腱板断裂が見つかったという方もおられます。この疾患は肩甲骨と腕の骨をつないでいる腱が加齢や外傷などによって切れてしまった状態です。残念ながらいったん腱が切れてしまいますと、自然にはくっつきません。時間とともに肩の機能は低下します。この肩腱板断裂により症状が長引いている場合には腱を縫合する手術が必要になることがあります。しかし、肩の腱は皮膚や厚い筋肉などの正常組織の奥深くに存在する部位に存在し、従来の大きく切開する手術(直視下手術)だと侵襲が大きくなります。当科では関節鏡を用いた低侵襲(体への負担が小さい)手術である鏡視下腱板修復術を積極的に行っています。
スポーツをする若年者における代表的な肩関節疾患としては反復性肩関節脱臼があります。いわゆる脱臼が癖になっている状態です。特にラグビーや柔道などのコンタクトスポーツ(衝突の多いスポーツ)をされている方に多く発症されます。初回の脱臼は衝突などの外傷を契機に生じることが多いです。この疾患は前述した保存加療では十分な効果が得られず、手術加療が必要になることが多いです。当科ではこの疾患に対しても関節鏡を用いた低侵襲で早期復帰を目指す鏡視下バンカート修復術を行っています(バンカートは人の名前です)。また野球選手に多い投球障害肩という疾患があります。これは投球フォームや関節の硬さが原因であることが多く、消炎鎮痛剤や炎症止めの注射で痛みをやわらげ、正しい投球フォームの習得やストレッチにて症状が改善することが多いです。
当科では適切な問診と身体検査や画像検査を行い、患者さん一人一人の病態を把握することで最善の治療を行うように心がけています。肩の症状でお困りの方はどんな症状でも構いませんので気軽に受診してください。
近年の主な手術件数
| 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年間総手術件数 | 338 | 352 | 352 | 390 | 470 | 532 | 465 | 330 | 523 | 555 |
| 骨・関節外傷手術 | 121 | 112 | 106 | 140 | 160 | 198 | 130 | 104 | 185 | 191 |
| 大腿骨近位部骨折 | 70 | 46 | 39 | 47 | 51 | 60 | 53 | 43 | 66 | 83 |
| 肩関節鏡手術 | 68 | 95 | 116 | 127 | 120 | 159 | 152 | 111 | 139 | 131 |
| 膝関節鏡手術 | 5 | 4 | 26 | 38 | 49 | 50 | 58 | 40 | 39 | 47 |
| 人工股関節手術 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 38 | 49 |
| 人工膝関節手術 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 16 | 18 |
当科の治療に関連する主な検査・設備
レントゲン・MRI・ヘリカルCT・エコー・骨塩定量装置・X線透視装置・RI・菌手術室
特殊外来につきまして
当科では、特殊外来として、乳児股関節外来を行っています。特殊外来の診療は、予約性で、非常勤スタッフが担当していますので、受診を御希望の方は、かかりつけの先生に紹介を依頼されるか、事前に、当科外来に連絡をいただいて受診可能か確認して下さい。
他施設との医療連携につきまして
当科は他施設との医療機関連携を大切にし、地域の医療機関からの紹介を積極的に受けています。 一方、御自宅の近くや夜間、土曜の診療、物理療法ができるクリニックなどでの治療を希望される場合は、対応可能な医療機関に紹介させていただいています。 なお、治療分野や内容によって、別の医療機関で専門的な治療を受けられることが望ましいケースもございます このような場合は、当科での治療に固執せず、より良い治療結果のために、より適切な治療を受けられる医療機関への紹介も積極的に行っています。
臨床研修医の皆様へ
当科は、奈良県立医科大学整形外科を中核とする関連研修施設です。一般的な整形外科の診療に加えて、肩・膝の関節外科、スポーツ整形、骨軟部腫瘍に関する診療の研修が可能です。
認定・指定施設一覧
日本整形外科学会認定制度による研修施設
医師紹介

| 診療科 | 整形外科 |
|---|---|
| 氏名 | 原納 明博(ハラノ アキヒロ) |
| 役職 | 部長 |
| 出身大学 | 三重大学 |
| 卒業年月 | 1995/3 |
| 学会資格等 |
(社)日本整形外科学会専門医 厚生労働省義肢装具等適合判定医 |
| 一言 |
膝・肩でお困りの症状、スポーツでのトラブル、お気軽に受診して下さい。 |

| 診療科 | 整形外科 |
|---|---|
| 氏名 | 松村 憲晃(マツムラ ノリアキ) |
| 役職 | 部長 |
| 出身大学 | 奈良県立医科大学 |
| 卒業年月 | 1998/3 |
| 学会資格等 |
(社)日本整形外科学会 専門医 |

| 診療科 | 整形外科 |
|---|---|
| 氏名 | 二階堂 亮平(ニカイドウ リョウヘイ) |
| 役職 | 部長 |
| 出身大学 | 奈良県立医科大学 |
| 卒業年月 | 2002/3 |
| 学会資格等 | (社)日本整形外科学会専門医 (公)日本体育協会公認スポーツドクター |

| 診療科 | 整形外科 |
|---|---|
| 氏名 | 尾﨑 裕亮(オザキ ユウスケ) |
| 役職 | 副医長 |
| 出身大学 | 秋田大学 |
| 卒業年月 | 2015/3 |

| 診療科 | 整形外科 |
|---|---|
| 氏名 | 桝田 義英(マスダ ヨシヒデ) |
| 役職 | 非常勤医師 |
| 出身大学 | 奈良県立医科大学 |
| 卒業年月 | 1984/3 |
| 学会資格等 |
(社)日本整形外科学会 専門医・指導医 |
| 一言 |
専門は、股関節の手術です。当院整形外科では、合併症の予防には十分に注意を払い、より安全な手術を心がけています。また充実したリハビリのスタッフとともに手術後の十分に機能回復をめざしたリハビリをさせていただきます。股関節の痛みでお困りの方は、是非ご相談ください。 |

| 診療科 | 整形外科 |
|---|---|
| 氏名 | 森下 亨(モリシタ トオル) |
| 役職 | 非常勤医師 |

| 診療科 | 整形外科 |
|---|---|
| 氏名 | 奥村 元昭(オクムラ モトアキ) |
| 役職 | 非常勤医師 |

| 診療科 | 整形外科 |
|---|---|
| 氏名 | 竹村 和生(タケムラ カズオ) |
| 役職 | 非常勤医師 |

| 診療科 | 整形外科 |
|---|---|
| 氏名 | 吉井 肇(ヨシイ ハジメ) |
| 役職 | 非常勤医師 |
■ 代表番号
![]()
受付時間(平日 9:00~17:00)
外来受付時間
午前 8:15~11:00
(午後診療については、外来診療担当表で各診療科ごとに確認して下さい)
休診日
土・日・祝日 ・(12/29~1/3)
13:00~20:00
子供の急な病気・ケガの時どうする?

または 0742(20)8119
平日
18時〜翌朝8時
土曜日
13時〜翌朝8時
日・祝・年末年始(12/29〜1/3)
8時〜翌朝8時
看護師や小児科医が電話でアドバイスします。
奈良県救急安心センター相談ダイヤル
救急車を呼んだ方がいいのかな?
病院で診察を受けるべきかな?
応急手当の仕方がわからない?
近くの医療機関が知りたい? などの場合…
お電話をおかけください。
プッシュ回線・携帯電話からは
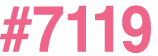
ダイヤル回線・IP電話からは

24時間受付!相談員や看護師が電話でアドバイスします。
医療安全相談窓口
医療に関する患者の苦情や
相談等の対応を行います。
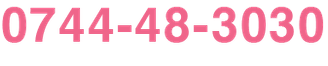
受付時間
平日 9:00〜12:00 13:00〜16:00
-
2024年06月19日 トピックス
【看護局】いきいき通信2024年 臨時号 -
2024年06月17日 トピックス
看護局研修報告 プリセプティ研修(ステップI) -
2024年06月14日 トピックス
看護局研修報告 術後疼痛管理 / フィジカルアセスメント -
2024年06月06日 採用情報
診療放射線技師(フルタイム) 募集 -
2024年06月06日 採用情報
ナーシングエイド(看護補助者) 募集

〒635-8501
奈良県大和高田市礒野北町1番1号
Google Map
【交通のご案内】
● 近鉄大和高田駅から1.2キロ(徒歩約18分、車約4分)
● JR高田駅から1.0キロ(徒歩約15分、車約5分)
● 近鉄高田市駅から0.7キロ(徒歩約10分、車約4分)
バス:大和高田市コミュニティバス(市内循環バス)きぼう号
葛城市コミュニティバス(環状線)
Copyrights(C) 2003 Yamato Takada Municipal Hospital . All rights reserved.